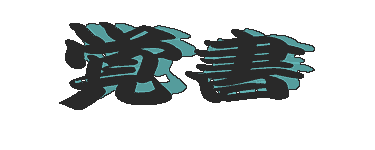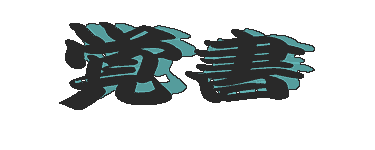
第1話 目利き自慢のこと
ここでは、注意・補足事項を中心に独り言を垂れ流しております。
この作品は、江戸時代がモチーフです。江戸時代と言っても長いですが、幕末が近い化政期(1804年〜1829年)を時代背景としております。
“エド”はもちろん“江戸”であり、“フカガワ”は“深川”ですね。
今回出てきた“ツクダ町”は“佃町”と書きます。作中通り、深川八幡社の前にある蓬莱橋を渡って左手側にありました。骨董市があると書いてありますが、これは私のでっち上げです。ただし、この町に稲荷神社があったのは本当ですよ。切絵図(当時の地図)にもちゃんと“イナリ”の文字が入っています。
私が参考にしているのは、嘉永2年(1849年)版のもの。想定しているのが化政期ですので、この切絵図は、ちょっと後の時代のものですね。切絵図にはわりと大きめに出ているので、そこそこに大きかったのではないかと推測しています。稲荷社の情景は、江戸名所図会だったと思うのですが、そこに出ていた別の稲荷社の情景を参考にしています。
次に、志輝というキャラクターが着ていた長羽織の縫い取りについて。
助六は、歌舞伎でお馴染みのヒーローの名前ですね。江戸っ子のスーパーヒーローだと、歌舞伎の本にも紹介されています。
さて、作中には『大江戸八百八町に〜』としか出ていませんので、ふぅん……程度のものでしかなかったかと思います。
これは、助六の名セリフの一部なんですね。『大江戸八百八丁に隠れのねえ、杏葉牡丹の紋付も桜に匂う仲の町、花川戸の助六とも、また揚巻の助六ともいう若い者、間近く寄って、面相を拝み奉れエエ』──というセリフです。
こんなセリフを羽織にあしらっている志輝というキャラクターの人柄を何となく感じ取っていただけたならと思います。
まだまだ勉強不足なのは重々承知の上ですが、ご贔屓いただけましたなら、幸いです。キャラヘのご質問などございましたら、こちらにてお答えさせていただきますね。では、ひとまず、これにて、了。
前頁 目次 次頁-->