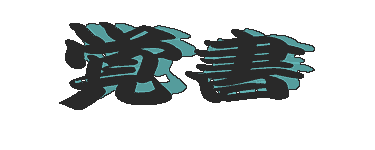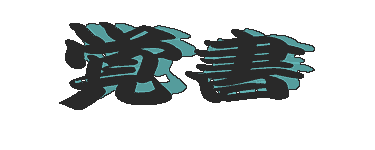
第2話 焦れる思いのこと
ここでは、注意・補足事項を中心に独り言を垂れ流しております。
まずは、地名から。“アイカワ町”は“相川町”。
“サガ町”は“佐賀町”です。地形が佐賀の湊に似ているから、この名前がつけられたとか。当時は、米や雑穀、油、干鰯などを扱う問屋や倉庫が軒を連ね、活気に満ちていたそうです。この町の河岸は「油河岸」とも呼ばれたとか。また、船宿も多かったらしいです。
相川町は、永代橋を渡って左側、右側が佐賀町になります。
さて、わかな・わかば姉妹が営む萬屋ですが、100円ショップをイメージしていただけたら、と思います。彼女たちの営む萬屋は私の創造の産物ですので、実際にあったかどうかは不明ですね。いくつか本をめくってみましたが、それらしい職業は見つかりませんでした。
100円ショップと彼女たちのお店との共通点は、こんな物まであるの?! と驚かされる品揃えの豊富さです。
現代の100円ショップと違うのは、「こんな物がほしい」という顧客1人1人の要望に答えてくれること。販売方式も現代のセルフ方式(品物を客がレジに持っていって会計する方法)ではありませんし、商品も○○文(円)均一ではありません。
ただ、38文均一という安売り店が文化7年(1810年)に出現していたそうです。翌年には、12〜19文の大安売り店が多くできたとか。
昔の人も安い物に惹かれていたのかと思うと、現代とあんまり変わりないなぁと思ってしまいます。
ちなみに、1文を現代のお金に換算すると、まぁだいたい30円くらいだそうです。計算方法や何を基準にするかによって、多少のばらつきはあるみたいですが、とりあえずこれを目安に換算すると、38文は1140円。12文で360円、19文で570円ということになります。
今回作中に出てきた職業は、医者と陰陽師。(茶汲み女や左官については、説明するまでもないと思いますし、影同心については後ほど作中で説明しますのでしばしお待ちを)
江戸時代、医者として開業するのに免許は必要ありませんでした。ですので『薬屋に毛のはえた奴頭剃り』なんていうこともあったようです。「頭剃り」というのは、当時のお医者さんは坊主頭にしていた人がほとんどだったからですね。
誰でもお医者さんになれたわけですが、当然、評判が悪いと誰も寄り付かなくなるので、自然と腕のよいお医者さんだけが残っていったようです。
さて、陰陽師ですが、正しくは宮中の陰陽寮に所属して、陰陽道に関することをつかさどる職員のことでした。つまり、官職だったわけですね。ところが、江戸時代に入りますと、民間にあって加持祈祷を行う者の称となりました。庶民にとっては、易者と同じように占いなどを行う業という認識だったそうです。
当てにならないと思われていた陰陽師ですが、許状と呼ばれる営業免許によって認可される、公的な肩書きだったとか。
許状の発行は、京都に本家を持つ土御門家にておこなわれていました。この土御門家というのは、系譜をさかのぼっていくと安倍晴明にまでたどり着くというお家柄ですね。
当時は、全国に何万という規模で陰陽師がいたそうです。信心深い人たちが多かったということですから、それだけの数の陰陽師がいても商売がなりたったのではないでしょうか。
この何万という陰陽師の中には、三河万歳などを行う門付け芸人も含まれていたと思われます。というのも、彼らも許状を土御門家から発行してもらっていたのですよ。何でそうなったのかは……調べだすとキリがなさそうで……調べてません。
しかし、門付け芸人と陰陽師……我々の感覚からは、結び付けづらいものがありますね。
ご意見・ご感想、質問(キャラへのものも可)などございましたら、ご遠慮なくどうぞ。分かる範囲、答えられる範囲でお答えいたします。
では、ひとまず、これにて、了。
前頁 目次